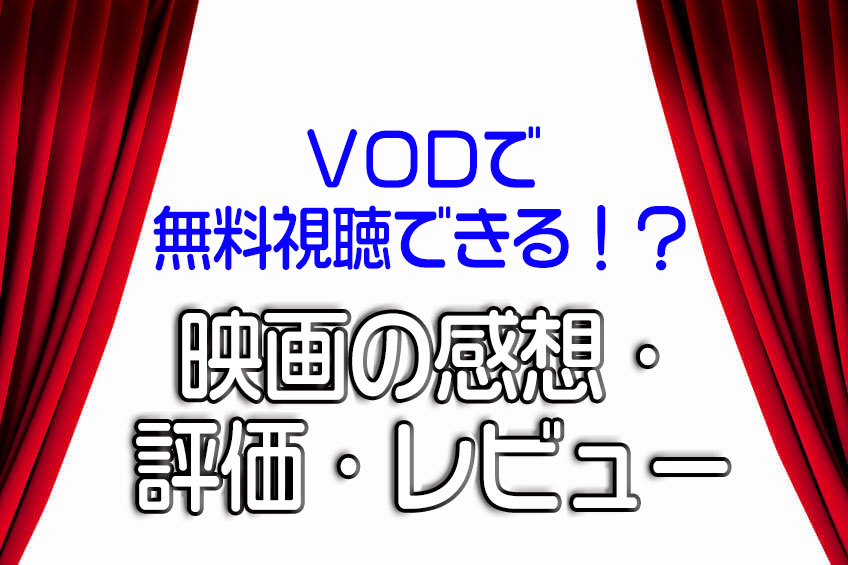【リンダリンダリンダ】の作品情報(スタッフ・キャストなど)
「リンダリンダリンダ」は2005年の日本映画です。
ガールズバンドを題材にした作品で上映時間は114分です。
監督をしたのは山下敦弘。
20代から活躍している若手の映画監督で、日本映画界のホープです。
主演はガールズバンドの4人です。
ペ・ドゥナと前田亜季、香椎由宇そして関根史織が女子高生を演じました。
映画は公開されてすぐに人気が出て、その年の日本映画の数々の賞を受賞し、各種の映画雑誌のランキングでも上位に入りました。
あらすじ解説
「リンダリンダリンダ」は地方都市の柴崎高校が舞台です。
文化祭「ひいらぎ祭」が前日に迫っていました。
山田響子は軽音楽部のドラムです。
ギターの今村萌が指を骨折したことにより欠員が出て焦っていました。
ボーカルの丸本凛子も出場を辞退するといったからです。
残ったメンバーは彼女の他に、キーボードの立花恵、ベースの白川望です。
3人は途方に暮れますが、部室にあったカセットテープをつけると、ブルーハーツの「リンダリンダリンダ」が流れます。
これを聞いた三人は「コレだ」と思って、急遽ボーカルを探すことにします。
バンドから離れていた凛子は、これを聞きつけてボーカルをやりたいといいますが、恵が反対しました。
そのやり取りの最中、偶然通りかかったのが韓国からの留学生ソンです。
ソンをなかば強引にボーカルに加えます。
文化祭の一日目が始まりました。
ボーカルが決まったはいいもののソンはまったくの素人です。
カラオケボックスで猛特訓が始まります。
恵もドラムからギターに変えて必死に練習します。
4人は初めての音合わせを行いますが、音は全く合わず散々な出来でした。
これでは文化祭に間に合わないと思った彼女たちは、学校に残ることで秘密の特訓を行います。
文化祭の二日目、恵はかつての恋人に頼み込んでスタジオを借りて4人は練習しました。
またも徹夜で練習した彼女たちはその夜も学校に泊まります。
日が明ける頃には4人の距離は縮まり、演奏は上達してきました。
文化祭の最終日、4人はバンド名を決めます。
韓国語で「青い心」を意味する「ザ・パーランマウム」に決定しました。
出番が来るのは15時30分ですが、4人は出番ギリギリまでスタジオで粘って最終調整を行います。
ところが連日の疲労がたたって4人はスタジオで眠り込んでしまいました。
出演時間がもうすぐというところで一人が目を覚まして、4人は急いで会場の体育館に向かいます。
その頃、指の骨折でメンバーから離脱した今村萌は4人のために時間を繋いでいました。
アカペラで歌っていると、その姿に魅了された観客が徐々に集まってきます。
4人が体育館に到着する頃には大勢の観客が集まっていました。
いよいよザ・パーランマウムのライブが始まります。
みどころのポイント
「リンダリンダリンダ」はコンテストに投稿された一つの企画から始まりました。
ストーリー企画があるコンテストで受賞を果たしたことで映画製作がスタートします。
ちなみにそのときの題名は「ブルハザウルス17」でした。
キャスティングで注目を集めたのはソン役を演じたペ・ドゥナです。
彼女は韓国の映画俳優で、今ではハリウッドの大作映画にも出演する大物女優です。
監督の山下敦弘は主役を誰にするか悩んでいましたが、彼女の映画を見たことで起用を決意。
ペ・ドゥナ自身も監督のファンだったこともあり、起用が実現しました。
また、立花恵を演じた香椎由宇は、この映画の演技が賞賛されていくつかの演技賞を受賞しました。
「リンダリンダリンダ」は女子高生がガールズバンドを組んで文化祭で演奏する、というストーリーです。
女子高生たちのキャラクター設定は現代的です。
いまどきの冷めた女子高生たちを描いており、彼女たちが部員の欠員というトラブルに見舞われて、その困難をどう乗り越えて、音楽の楽しさに気づいていくか、というストーリーになっています。
はじめは冷めていたのに、徐々に練習に熱が入っていくところは映画のみどころでしょう。
使われている楽曲はブルーハーツです。
ブルーハーツはバンド名を変えながら80年代から2000年代にかけて活躍したバンドです。
曲調も歌詞もとても熱いものが特徴ですが、そんな音楽に影響されるように彼女たちは熱いものに目覚めていきます。
実はキャストの中にはミュージシャンが多数出演していたり、音楽好きを楽しませてくれる要素もあります。
映画のいちばんのみどころはクライマックスのライブシーンでしょう。
約2分40秒のライブのために、この映画は作られたと言っても過言ではありません。
韓国人のペ・ドゥナは日本語の歌詞を歌うボーカルという難しい役どころを見事に演じました。
彼女が歌っている横顔を中心に、演奏しているメンバーが順々に映されていきます。
ライブシーンはエキサイティングですが、非常に抑えのきいたシンプルな画面構成をしており、感動が伝わる日本映画史上屈指の名シーンになりました。
今では山下敦弘監督のなかで人気の高い一本になっています。